
 |
|||||||
| トップ | 日記 | 飼育と採蜜 | ランとミツバチの捕獲 | ショップ案内 | ||
| 工作の部屋 | 観察資料 | リンク |
|
|
日記のページ
|
|||||
|
|
|
2010年6月26日 スムシの産卵活動が活発です 毎年、6月の中旬以降、スムシ成虫の産卵活動が活発化します。 今年も、スムシ捕獲器の粘着シートに卵を腹に抱いたスムシ成虫が張り付いています。 張り付いた蛾は、すべてそこで卵を放出しています。当然のことながら、捕獲器に張り付く蛾はメスのみです。子孫を残そうと、必死なのです。 大きい方の蛾がハチノスツヅリガで、幼虫は良い釣り餌ですが、蜂にとっては厄介者です。 小さいほうの蛾がウスグロツヅリガです。 別の蜂場の巣箱には、スムシ捕獲器を設置していませんでしたが、巣箱のまわりに侵入を伺っているハチノスツヅリガが数匹も取り付いていたので、急いで設置してきました。 強群の巣箱の方の捕獲器のほうが、スムシ成虫の入る数が多いです。 強群の巣箱からは、より大量の蜂の臭気が発散されるので、結果的にスムシ成虫を多く呼ぶことになるようです。 今のところ、ハチノスツヅリガとウスグロツヅリガの捕獲数は同じくらいです。 6月18日の継ぎ箱画像のその後です。 少し大きくなったくらいです。 上の画像は、この春人工分蜂した箱の様子です。9枚の巣枠の群を3枚づつ3群に分けたもののひとつですが、どれも同じ経過をたどるとは限りません。思うように増群しないのもあります。 これは最強群で、人工分蜂してから約50日で巣枠9枚全部増巣して、観察窓から見える一番端のこの巣枠にもほぼ全面に働き蜂の蛹蓋がかかっています。10日もすれば次々に羽化して、継ぎ箱にも蜂があふれてくるでしょう。 このような状態で継ぎ箱をしないで、放置すると、やがて王台を作り分蜂準備をしてしまいます。 この時期からの新たな分蜂群は、秋までに大群になりにくく、採蜜はほぼできないでしょう。 越冬がやっとの群にしかなりません。 やはり5月の連休頃の分蜂群が、順調に成長してくれます。 ※人工分蜂の手順は近日更新いたします。 2010年6月18日 継ぎ箱をしました 巣箱容量の7割ほどまで増巣して、その勢いが止まらないようなので、継ぎ箱をしました。 この群は、下に継ぎ箱を入れました。 蜂数が多かったので、すぐに下段に降りてきて、増巣を始めています。 下に継ぎ箱を入れると、画像のように巣枠に添って上から降りてきます。 下段の巣が成長すると、育児圏も下段に降りてきて、上段は蜜巣になります。 一度育児をした巣房に蜜を貯めてゆきます。 参考までに、上に継ぎ箱をした去年の画像を添付します。 上段に継ぎ箱をした場合は、下から巣を盛り上げています。 この場合、巣枠とは関係なくでたらめに巣を盛り上げますので、巣枠による操作はできなくなります。しかし、育児をしていないきれいな巣に蜜だけを貯めますので、きれいな、香りの良いハチミツが貯まります。 下段で子育てが継続していて、秋には下段にも蜜を貯めるので、上段(継ぎ箱)を全部採蜜することになります。 アカシア、ノバラが終わりイタチハギが開花しています。 ミツバチはこの花が大好きで、この時期になると、鮮やかな色のこの花の花粉をつけて巣箱に戻ります。 2010年6月11日 新蜂が羽化し始めました 5月7日捕獲群の成長の様子です。 7日に待ち桶に入り、その日に観察窓付き飼育箱(巣枠式)に取り込みました。 その後、順調に増巣していました。6月4日には6枚目の巣枠に巣を作るまでになりましたが、まだ新蜂が羽化していないので、蜂の数が徐々に減少してゆき、巣板が見えるようになっていました。 そして6月10日に見ると、新蜂がいっせいに羽化し、蜂の数が爆発的に増えています。こうなると、日ごとに蜂数が増えて増巣スピードも速くなりますので、継ぎ箱の準備をしておかなければなりません。 天候も順調なので、1週間後には継ぎ箱の予定です。 遅れると、巣箱がいっぱいになり、王台を作り分蜂の準備をする恐れがあります。 私の蜂場(新潟地方)では、天候がよければ蜜が貯まり続けます。真夏でも蜜源花があるらしく、夏枯れ(夏に蜜源がなくなり、貯蜜が減少すること)というがありません。参照 冬以外で巣箱重量が減少するのは、梅雨と秋の長雨の時期だけです。 ミツバチにとっては、遅く入梅して早くあけてくれると都合が良いのですが・・・。 2010年6月9日 ノバラも咲き始めました 蜂場の近くの道路脇に繁殖する雑草(落葉低木)ですが、ミツバチは大好きです。 園芸品種のバラより、やさしく、控えめな、上品な香りがします。 分蜂後に産卵して生まれてきたニホンミツバチの新蜂は、体色も黄色がかって、セイヨウミツバチと間違えやすいものもあります。 しかし、体格はセイヨウミツバチより一回り小さく、羽音が少々高いです。 ニホンミツバチの羽音は、C(ド)の音ですが、セイヨウミツバチは半音低いB(シ)のようです。 2010年6月7日 木苺の花が大好き 数年前たった一株もらってきた木苺(ラズベリー)が大繁殖。雑草のように強い植物です。 この花を、ニホンミツバチが大好きなのです。セイヨウミツバチもたまに見ますが、ほとんどがニホンミツバチです。近所の庭の花にも訪花しているのか、観察してみたところ、我が家の木苺だけにニホンミツバチが訪花しているようです。それも毎日、多数。 どんな香りがするか、と思ったら木苺の花はなんの香りもしませんでした。人間にはわからないものをミツバチは感じ取っているようです。 この木苺は、果実でジャムを作ります。木苺とハチミツだけで作ると、お店で売っているどんなジャムより美味しいものができます。作り方は後日公開します。 シロツメクサも大好きです。この花は良い香りがします。 春は、バラ科の植物とマメ科の植物がミツバチの主な蜜源になっているようです。どの花も、良い香りのする良質の蜜源です。 バラ科は、ウメに始まり、各種サクラ、ノバラ、キイチゴ等。 マメ科は、ニセアカシアを筆頭に、フジ、クローバー、イタチハギ等。 これらの植物が切れ目なく次々と開花して、天候さえ良ければ順調に蜂群が成長し、大量のハチミツが貯まります。 2010年6月4日 アカシアが満開です ニセアカシアが満開になりました。幸い天気も良く、気温も高い状態が続くので、ミツバチは順調に蜜を採取しているようです。 私の群は、5月5日前後に捕獲、人工分蜂した群なので、そろそろ新蜂が出てくる頃です。 今年は、春の寒波の影響で、今頃になっても捕獲の報告が続いています。 例年なら、分蜂の時期は終わっているのですが、山間地だけでなく、平地でも分蜂が続いています。私はとっくに待ち桶を撤去しているので6月の捕獲はありません。 今年初めて捕獲に挑戦した人(4月から捕獲できずにいた)から、初めての捕獲の報告があると、私もうれしくなってしまいます。 6月の捕獲は、秋までに越冬に十分な蜜を貯められるので、給餌をする必要がありません。しかし余分な蜜も少ないので、秋の採蜜は味見程度になるでしょう。 たくさん採蜜をして、給餌をして冬越しをすることは避けたほうが無難です。 自らが集めた蜜で冬越しをしてもらいましょう。 5月6日捕獲群は6枚目の巣枠に巣を作り始めています。順調なら6月中旬〜下旬に継箱をすることになるでしょう。秋には十分な量(10キロほど?)のハチミツを採蜜できるでしょう。 2010年5月31日 アカシアの花がもうすぐ開花します ニセアカシアが開花直前です。 画像は蜂場付近の花の様子です。 これから10日ほど天気が良い予報なので、きっと大量の蜜を集めるでしょう。 今の時期は、凄い勢いで巣の増設と、新蜂の生産をしています。もう10日もすれば大量の働き蜂が羽化して、蜂数も増えるでしょう。 2010年5月23日 美味しい春蜜 先日、待ち桶に入った群が、待ち桶の中に半日で作った巣です。 巣枠式巣箱に移したら、待ち桶に残っていました。 中にはハチミツが少々入っていたので試食してみました。 このハチミツのおいしいこと!ほどよい酸味と華やかな花の香り! ハチミツ特有のにおいが感じられません。まさに花の蜜です。 ハチミツも熟成が進むと、ミツバチの体臭のような特有のハチミツ臭が強くなりますが、 この時期しか味わえない特別なハチミツです。ミツバチを飼っている人しか味わうことの出来ない極上のハチミツです。 はたしてセイヨウミツバチの場合はどうなのか、知りませんが、 市販されているどんな上等なハチミツより美味しい蜂蜜です。断言できます!格が違います! このようなハチミツを採取して、皆さんに味わっていただきたいのですが、この時期は採蜜出来ません。残念です。秋の採蜜時期までには熟成も進み、ハチミツ特有のにおいが少々入ってしまいます。(それでも美味しいのですけれど・・・・) 熟成が進んでいないので、糖度も低いのかと思い、計ってみました。 糖度計に一滴落として、計ってみると78度ありました。発酵しない糖度です。 春のこの時期、蓋掛されていない巣の蜜は70度前後と予想していましたが、意外な結果でした。 糖度計の接眼部にカメラを当てて撮影できたことも意外でした。 秋にこのようなハチミツが採れたらなぁ・・・。 2010年5月20日 スムシが産卵活動を開始しました 上画像のアクリル板の観察窓に止まっている3匹のうち、 右下の奴がスムシ成虫(ハチノスツヅリガ)です。 触覚をせわしく動かして何かを探っているようです。 産卵ために夜中に巣箱に侵入したものです。去年より5日ほど早い確認です。 こいつらは1度巣箱に入ると、腹の中の卵を全部産み付けるまで出て行かないようです。 憎たらしいスムシによる被害を少しでも軽減するために・・・。 この時期はほとんどハチノスツヅリガの産卵ですが、 今年は少し詳細なデータを取って、ハチノスツヅリガとウスグロツヅリガの産卵の傾向を調べてみたいと思っています。 2010年5月18日 私の箱にも入りました 里山の神社の床下です。 午前8時30分頃、多数のミツバチが出入りしています。 ミツバチの数が100匹以上で、傍らのキンリョウヘンにも興味を示さず 箱を出入りしているので、入居するようです。 午後3時頃の見回りで入居を確認し、すぐ巣枠式の巣箱へ移し変え、 夜、10キロほど離れた蜂場へ移動しました。 2010年5月17日 気温が上がりまた分蜂し始めました 友人の待ち桶に昨日、今日と1群づつ入りました。 巣枠式巣箱を直接待ち桶にしているので移し変えの手間が要りません。 どちらも知人宅の敷地内に仕掛けておいたので、盗難の心配がないので、 直接、飼育箱を待ち桶にすることが出来たのです。 調べてみると、入居した箱から100メートルほど離れた神社の床下から、 多数のミツバチが出入りしていました。 おそらくこの自然巣からの分蜂群でしょう。 2010年5月13日 寒冷前線通過、冬型の天気です 寒くてミツバチも活動していないので、先日のウワミズザクラの様子を紹介します。 とてもよい香りのする花で、よい香りの蜜を出します。 この花がサクラの仲間だとは思いませんでした。 ミツバチを飼う前は、こんな花があるとは思ってもいないくらいでした。 晴れて気温が上がると、あたり一面よい香りが漂います。 2010年5月9日 今のところ捕獲は不調です 今年の捕獲はなかなか不調で、待ち桶にも探索蜂の数が少ないです。 昨日、今日と気温も低く、成績が上がりません。 皆さんのところは、どんなでしょう? 6日に捕獲した群が不穏な動きをしていました。落ち着きがなく、巣箱の周りを飛び回り、巣箱の外に付いて夜を明かす蜂も出てきました。 たぶん今日か明日にも逃去するつもりのようです。 そこで9日朝、女王蜂が出られないように巣門を狭くしました。 アルミ缶をハサミで切って、板を作り画鋲で止めました。閉じた状態から徐々に上げていって、働き蜂がかろうじて出られる高さで画鋲で止めます。 昼間、逃去しようと働き蜂が出て大騒ぎしますが、女王が出られないのでまた元に戻ります。たぶん交尾を済ませている旧女王でしょうから、産卵して育児が進むまで、この状態にしておきます。 2010年5月6日 探索蜂の来ていなかった箱に入りました。 5月4日にキンリョウヘンを切花にしてさしておいた待ち桶に突然の入居です。 探索蜂がまったく来ていなかった箱です。付近の分蜂はまだ先かなと思っていたら、夕方の見回りで捕獲判明です。箱を鉛筆でコンコンすると、ザーッと羽音がします。 花に網を被せていなかったので、ミツバチの熱で半分しおれています。誘引力は弱くなっていると思いますが、次の花が咲かないので、このまま使用することにします。 この待ち桶では飼育しないので、巣枠式巣箱に強制収容します。 次の日になると、待ち桶に巣を作ってしまうので、その日に移し変えをします。 午後3時半頃、待ち桶の手前に巣箱を置いて、蓋を取り、 巣枠を5枚ほどはずします。 待ち桶をそーっと持ち上げ、飼育箱の上に移動します。待ち桶の中を下から見ると天井に蜂玉となって付いています。 はずした巣枠のところへ、蜂玉を落とすわけですが、移す手順のように巣箱の角にコンと当てれば、ドサッと落ちます。 すばやく、慎重に、巣枠を入れて、蓋をします。これで終了。 ドサッと蜂を入れてから、蓋をするまで約1〜2分です。短い時間で作業するほど、ミツバチにストレスがかからず、定着率が上がります。 強制収容直後の画像ではよく映っていませんが、凄い数のミツバチが舞っています。しかし、30分もしないうちに巣箱に収まってくれます。 夜7時頃、すべての蜂が巣箱に収まり、蜂玉を作って落ち着いている時に移動します。 毎日50匹前後探索蜂が来ている箱に入らないで、まったく予兆無しの箱に突然入ったりするので、どのような状態になると入るのかは、よくわかりません。 初めての人が捕獲をめざす場合、なるべく多くの待ち桶をいろんなところに置いて、捕獲に適した場所を見つけるというのが、大事なのではないでしょうか。一度捕獲した場所は、ほぼ毎年捕獲できるので、そのような場所を3〜4箇所見つけておくと、毎年無駄のない捕獲ができるでしょう。 2010年5月4日 捕獲第1号 昨日、捕獲に失敗した箱に、第2分蜂と思われる群が入居しました。 3日の日記の木の洞に、入札で負けた箱に翌日午後2時頃入りました。 キンリョウヘンは、切花にしてあります。 昨日2日新潟地方の平野部では、いっせいに分蜂がはじまりました。 待ち桶、キンリョウヘンに、探索蜂が多数寄ってきました。 画像の待ち桶(神社の境内にある)に、朝多数の探索蜂が寄ってきましたが、 9時30分ごろ、20メートル離れた木の洞に入ってしまいました。 自然の物件には勝てませんでした。 残念ですが、第2、第3の分蜂に期待することにしました。 2010年5月2日 誘引ラン各種 咲き始めたキンリョウヘン原種とミスマフェットアルバ(白花)です。 本日待ち桶を設置している神社の境内に持って行って、探索蜂が来るか、検証しようと思っています。天気も良いし、風も弱そうです。 なんの変哲もないシンビジュームの花が、ミツバチを誘引すると言う不思議な現象があるおかげで、その花がとても美しく見えてしまいます。誘引力が強いほど綺麗に見えてしまいます。 誘引力が強いキンリョウヘン原種とミスマフェットアルバ(白花)の美しいこと・・・・。 蜂飼いでない普通の人の目からみれば、交配品種であるフォアゴットンフルーツのほうがはるかに華やかで美しいのでしょうに、私たちミツバチを飼う人にとっては、地味なキンリョウヘンやミスマフェットの方に、秘めた力強い美しさがあるように見えます。 花の色合いがそっくりです。 ミスマのほうが少し花が(葉も)大きいようです。ミスマの花は下垂します。交配親のデボニアナムの性質を受け継いでいるからですが、よくこの白い色が出たものです。 キンリョウヘンも斑入り葉でないほうが、丈夫そうで好きです。 2010年5月1日 昨日、各所に待ち桶を設置しました 5月1日から天気も良くなり、気温も上がる予報なので、ようやく巣全巣の分蜂群を捕獲するための待ち桶を設置してきました。 車に約10箇所分の待ち桶を積み込んで、出発です。 神社6箇所と、知人の庭、畑の脇に4箇所、設置してきました。 昨日はまだ寒く、風邪も強いので探索蜂は確認できませんでしたが、今日からは探索蜂も出てくるのではないでしょうか。 特に5月3日、4日は気温も上がりそうなので、分蜂が始まる予感がします。 キンリョウヘンはまだ満開に至らないので、設置していません。 私の場合、神社の管理者(区長さんなど)にはすべて了解を得て設置していますので、トラブルになることはほとんどありません。 事前に管理者にお会いして、神社に寸志をお供えしています。 私もいい大人ですから、そのくらいのことはしないと・・・。来年もありますし。 知人には、ハチミツなどを・・・。 これで安心して設置、見回りができます。 この単純な箱にミツバチが入るとは思えない人も多く、私も見回りますが、興味を持った人が時々見回りをしてくれているようです。 「今日は蜂が来ていたよ」とか「今日はぜんぜんいませんでしたよ」と報告してくれます。 大群が来て、箱に入るところを見たら、きっと自分もやりたくなるでしょう。 新潟地方はこれからが分蜂期ですが、東北、北陸各県もおなじと思います。 私の地方では、ニホンミツバチを捕獲飼育している人はほとんどいません。私と、私の蜂友が少々いるだけです。 捕獲する場所での取り合いなどは、皆無の状態です。 ニホンミツバチに対する認知度もかなり低く、その飼育などは思いも及ばないことのようです。 特に、私が捕獲場所にしている、ミツバチの密度が濃い里山付近の人は、今のところ蜂にまったく関心がないようです。 信州の人と、越後の人の蜂に対する思いは、かなり大きいものがあるようです。 2010年4月28日 自然群の探索蜂を確認、分蜂に至らず
しかし、待ち桶が倒れるほどの強風が吹き荒れ、午後には探索蜂も見えなくなりました。 今日、明日と雨の予報で、30日から晴れて気温も上がる予報ですので、30日以降、分蜂の可能性が大きいです。 ここに来てようやく私も待ち桶を設置する準備をします。 28日に待ち桶にミツロウを塗り、29日仕掛けてきます。 いつもの年なら、散ってしまって葉が出てくるソメイヨシノが、25日で画像のように満開状態で、 今日28日朝でも花が付いています。 こんな状態ですから、分蜂は遅れるものと思っていたら、結局例年並みに5月1日前後となるようです。 ランの開花が遅れていて、画像のような状態です。 このミスマフェットの白花は、少しでも開けばミツバチを呼びます。 4月30日までにはもう少し開花するでしょう。 今年はミツロウ、ランのほかに、ニホンミツバチを誘引するものがないか実験中です。 効果が認められるようなら、公開します。 2010年4月26日 私の飼育群も分蜂! 先日の寒波の影響で遅れると思ったら、巣箱の中の新女王は元気に育っていたのですね。 去年と同じに波板のところに集まりました。 でこぼこで取り込むのに苦労します。 1、この元巣から出ました。 2、空いている巣箱に蜂球を移しました。 画像下に青いネットが見えますが、そのネットで蜂球をすくい、箱の蓋を取り巣枠を4枚ほどはずして、放り込みます。すぐに巣枠を戻し蓋をしますが、ミツバチは大騒ぎです。 3、でも30分後には全部巣箱に収まり静かになりました。 元巣をすぐに人工分蜂します 元巣には各巣枠に2〜3個ほど王台が付いています。蓋の開いたものもあります。 働き蜂の巣房、雄蜂の巣房、王台が見えます。 王台が付いた巣枠を確認して、空いた巣箱に入れます。 元巣を、2分します。 最初の分蜂で、旧女王は出ているので、分けるときは、必ず元気そうな王台が付いた巣枠を入れます これで3つに分かれました。 その日の夜、別の蜂場に移動しました。 各巣箱が、順調に育ってくれるように祈るばかりです。 自然王台による、人工分蜂の手順は、近日飼育のページで詳細を公開します。 自然巣の分蜂はまだ確認していません。 2010年4月22日 分蜂第1号確認 私の蜂友の飼育群が昨日(21日)に分蜂しました。 蜂友の庭においてある飼育群から5メートルほど離れた犬小屋に入っていました。 画像の蜂球は、カメラをそっと突っ込んで下から撮影しました。 バレーボールほどの大きな蜂球が、犬小屋の天井に付いていました。 この時期のニホンミツバチは、攻撃性がまったくないので、面布などはいりません。 蜂友も分蜂は5月に入ってからだと思っていたので、まったく予測していない分蜂だったそうで、その日の午後3時頃、犬小屋から蜂が出入りしているので中を覗いたら、蜂球があったそうです。 その日の夕方、巣枠式の巣箱に移して、別の蜂場に移動するそうです。 例年より10日ほど早いこの分蜂は特別早い分蜂で、この群の個性ではないでしょうか。 分蜂後の元巣はまだ蜂で一杯ですから、近日中にもう2〜3回分蜂するでしょう。 これで、新潟地方が分蜂期に突入したとは言えないでしょうが、その時期はもうすぐです。 待ち桶を設置するなどの準備をしてもいい時期が来たと言えます。 自然巣の分蜂はもう少し先になるのではないでしょうか。 2010年4月21日 年間の増加と越冬の減少の関係 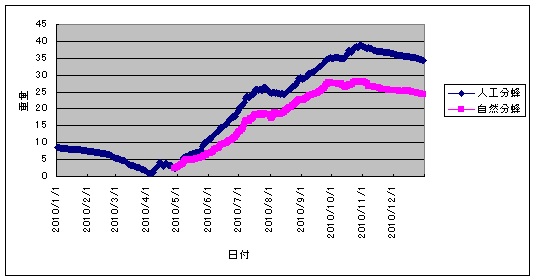 年間の巣箱の重量変化 ※日付は2010年になっていますが、2009年からの統計を編集しました。 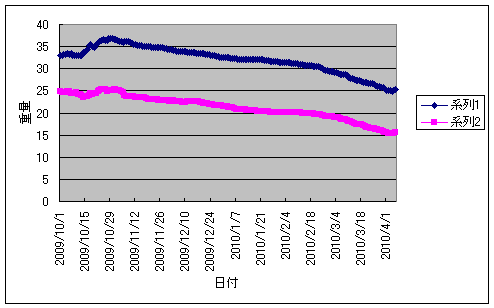 冬季の巣箱重量の減少 上記のグラフから、ニホンミツバチは年間25〜35キロの蜜を貯めることがわかります。 冬の貯蜜消費量は、どの群もおおむね12〜13キロほどです。 貯蜜不足にならないように15キロほどの蜜を残せば十分越冬できることになります。 貯蜜から消費分を引いた10〜25キロが採蜜可能な量になります。 貯蜜が多い蜂群は20キロほど、巣箱1段分採蜜できます。 少ない群でも巣枠3枚ほど採蜜できます。 一家の消費には十分な量です。近所におすそ分けもできます。 秋の採蜜をめざして、まずは捕獲です。 分蜂期はもうすぐです。 2010年4月20日 やっとソメイヨシノが開花しました。 寒さの影響で開花の遅れていたソメイヨシノが、やっと開花しました。 大量の蜜を吹くソメイヨシノですが、花を割ってみました。 ツマヨウジの先のところに蜜が光っているのがわかるでしょうか。 とても美味しい蜜です。 サクラのおかげで、分蜂に向け活発に活動できるようです。 もうすぐ開花します。4〜5日後でしょうか。 開花してから、満開になるまで10日ほどかかります。 今年は、29日に待ち桶を設置しに回ろうと思います。 とうとう分蜂期がやってきます。 2010年4月14日 美味しいピザが焼けました 3月16日の画像がぼけていたので、再チャレンジしました。 自作ピザ焼き釜です。ホームセンターで販売している安いバーベキューコンロを改造しました。 ピザを入れて2分もすると、チーズがとろけて焼けて泡だってきます。同時にいいにおいが・・・。 4〜5分で焼き上がり、外はパリパリ、中はもっちり、チーズはとろーり、ピザ専門店の石釜で焼いたものと同じ焼き上がりです。 このピザ焼き釜は、誰でも安価で製作できて、場所をとらず、どこでも持ち運び可能です。 上部で焼肉もできる優れもの! 近日、このピザ焼き釜の作り方を公開します。まっててね。 次の画像は本日の蘭の花芽です。 だいぶ花芽が伸びてきました。28日頃開花の予定ですが・・・。 フォアゴットンフルーツは、片親がミスマフェットらしいです。どうりでミツバチを誘引するわけです。でも誘引力は弱いです。 2010年4月11日 お宝発見 先日、農家の住宅のトイレに手摺を取り付ける工事をして、工事終了後、物置小屋を見せてもらいました。現在使わなくなった農具があれこれ積み上げられて眠っていました。 その中で、私の目を引いたのがこれ。 1斗枡です。杉かサワラか、大変軽くできていています。 一目見て、使える!!と思いました。待ち桶にぴったりではないですか。 古くなって色あせた具合なんか最高です。何十年も前のものなので、木の匂いやアクも抜けています。これはミツバチの好みそうな丸桶です。 まだ使いますか?と聞いたら、捨てるつもりとのこと、もちろんいただきました。 丸太をくりぬくと、どうしても重くなりがちですが、これなら大丈夫です。 皆さんの周りにもこんなお宝が眠っているのではないでしょうか? 画像は10日の昼過ぎの様子。雄蜂も姿を現し、分蜂期も近い様子。 巣箱の前を横切っても平気です。攻撃モードは消えました。 この箱の分蜂は25日頃でしょうか? 2010年4月6日 巣箱重量増加!本格的春突入 梅が満開になり、減少していた巣箱重量が増加し始めました。こちら とうとう春に突入です。貯蜜不足の心配はもういりません。 去年と同じ5日から増加し始めました。 去年の飼育群の分蜂が4月28日で、自然群が5月1日にいっせいに群蜂しました。 平年並みの天候で、ソメイヨシノが10日に開花すると、今年も初年と同日付近に分蜂すると思われます。 分蜂まであと1ヶ月を切りました。なんだかそわそわします。 新潟より暖地の方は、もう目前ですね。目標の群数を捕獲したいですね。 今年は10群捕獲したいのですが、どうでしょう・・・。 2010年4月3日 そろそろ人工分蜂の準備をせねば・・・。 新蜂も順調に増え、分蜂期までおよそ1ヶ月となりました。 人工分蜂のために、めったにやらない巣箱内の整理をする時期になりました。 私は、ほとんど巣箱の整理、掃除をしないので、蜂たちは好き放題に巣を結合して、このままでは巣枠を取り出せないので、この時期に結合した巣枠を分離する作業を行います。 ケーキ作りに使うクリームを塗るナイフで結合部分を切ってゆくのですが、女王を傷つけないように慎重に行います。 晴れて気温が上がった日に行う予定です。その模様は後日掲載します。 2010年4月1日 ようやく春が・・・ 画像では少し判別が難しいですが、モルタルの土間にナメクジの這い跡が見えます。 雪割草の鉢から出てきたらしいです。 3月27日に撮ったものです。まだ寒いのにナメクジ、カタツムリも活動を始めました。 鉢の中に潜んでいて、夜に出てきます。キンリョウヘンの花芽を食害する蜂飼い泣かせの害虫です。 去年はミスマフェットの花芽を食害されましたが、今年はナメクジよけのおかげで、ランの被害はゼロでした。1年間大事に育てた花芽ですから、ナメクジなんかに食べさせません! 2010年3月26日 今年の計画 その3 今年は巣枠式巣箱飼育で、女王蜂の育成による女王の更新と増群に挑戦してみます。 ニホンミツバチでは難しいとされる意図的な王台形成の技術を会得しようと思います。 私の使用している巣枠式の巣箱で、簡単に誰でもできる女王育成を目指します。 今までは、春の分蜂期に作られた王台を利用しての増群でした。分蜂期以外では王台を形成したことがありませんでした。思いつくことをあれこれ試して、人工的に王台を作らせて見たいと思います。この技術を会得している方もいらっしゃるようなので、不可能な技術でもないようです。 誰でも簡単にできる技術として確立したいと思いますが、今年中にできるかどうか・・・。 花芽の様子です。 4月の25日に開花、5月1日満開となれば、理想なのですが・・・。 2010年3月24日 今年の計画 その2 計画その2は、捕獲した分蜂群の増巣の様子をスライドショーで記録公開することです。画像は巣枠3枚入っていますが、実際は9枚全部入れます。勢いの良い蜂群だと、6月末までにいっぱいになると予想していますが、どうでしょう。 5月6月7月は、増巣の勢いが早いので、3日ごとに撮ることになると予想していますが・・・。 2010年3月20日 今年の計画 その1 今年は、蜂場の四季の移り変わりを定点カメラで撮影し、このHPで スライドショーでお見せしようと思います。 本日、天気も良かったので定点カメラ用の台を設置して、まずは1枚撮りました。 ここは、ヤマザクラから始まって、夏まで次々と花が咲きます。 良蜜の蜜源があるので、ハチミツもとても上質です。 ヤマザクラが咲いてから、ミツバチをここに持ってくるので、ヤマザクラの蜜は入りませんが、次に咲くウワミズザクラの蜜が入ります。蜂場付近はウワミズザクラの木が多数生えています。 画像は、ウワミズザクラの本日の芽の状態で、花はこんなです。 非常に良い香りがする花で、蜜もまた上質です。とてもサクラとは思えない花ですが、サクラの仲間です。この花が咲くと、付近は数日良い香りが漂います。 ミツバチがこの花の蜜を集めるので、巣箱からも、爽やかな、甘い香りがします。 この花が終わると、ニセアカシアが開花します。 定点カメラでこの花の開花の様子をお見せできると思います。 2010年3月16日 自作ピザ焼き釜 冬は雪に閉じ込められる新潟地方にあって、外遊びが好きな私は無性にバーベキューなどをしたくなります。 数年前、ただの焼肉や、焼きそばに飽き足らなくなり、美味しいピザを焼いてみたくなり、試行錯誤の結果完成したのが、このバーベキューコンロを改造したピザ焼き釜です。 焼き上がりの画像がピンボケなので後日再掲載したいと思います。 このピザ焼き釜は、安物のバーベキューコンロを改造したものですが、焼き上がりがまるで石釜で焼いたピザと同じの優れもの。 高温で上下から加熱して焼くので、約3分で焼きあがります。 中はもっちり、外はカリッと焼き上がり、子供たちも大喜び。 キャンプ場などでこの釜でピザを焼いていると、周りの人が驚きます。 我ながら、自慢、自慢。 簡単に製作できるので、後日きれいな画像と共に、ピザ焼き釜の作り方を再掲載したいと思います。 2010年3月10日 秋田の天然温泉 秋田県の八九朗温泉は天然ジャグジーの温泉です。 40度ほどのちょうど良い湯加減で、湯壷の真ん中から大量の泡が吹き出ています。 ここは、数ある無料原始温泉の中でも、最上級の温泉ですが、新潟からでは、高速道路を乗り継いでも7時間ほどかかります。 人が手を加えていない自然のままの温泉が、こんなにも気持ちのよいものだと言うことを、教えてくれる温泉です。 マニアの中でも結構有名な温泉ですので、検索すると多数ヒットします。 天然の湯壷がありますので、タオル1本あれば原始温泉初心者でも快適に入浴できます。 もちろん混浴で、脱衣所はありません。 2010年3月6日 消滅目前の群が・・・ 健全な群なら2月の末ごろから、天気が良く気温の上がった日は、巣箱からたくさんの新蜂が飛び出してきますが、何かしら問題のある群は、蜂の出入りが異常に少なく、その蜂の色も黒く、攻撃的です。 写真はそんな、群の底板を引き出してみたところです。(引き出し式の底板は掃除に便利です) 齧り落とした巣屑に、なにやら落ちています。 良く見ると、大量の雄蜂の巣蓋です。 どうやらこの群は、越冬中に大量の雄蜂を生産した模様です。原因は女王蜂が事故死か寿命死でいなくなり、激しい働き蜂産卵が起きたものと見られます。厳寒期にこのような状態になると、群の消耗も激しく、あっという間に消滅してしまいます。 健全群は蜂の出入りも多く もちろん雄蜂の蓋はほとんど無く、新蜂も加わり蜂数も多いので、底板に積もった巣屑も外に運び出しています。落ちた巣屑の中にはスムシはいませんでした。 巣箱の掃除をした結果 例年、巣箱内にはスムシがたくさん潜んでいるのですが、今年はこの1匹だけ目視できました。 スムシ捕獲器による成果かな、と思っているのですが。 今年もスムシ捕獲器を設置して、ハチノスツヅリガとウスグロツヅリガの個別産卵統計を取ります。ハチノスツヅリガとウスグロツヅリガの産卵時期にはどんな違いがあるのか、解明できればと思います。 2010年2月25日 本日最高気温22度! 黄色い花粉をつけて戻ってくる蜂が数匹見えます。 今日の気温は、2月の最高気温の記録を更新する22度まで上がりました。 ここ胎内市は新潟県で一番高くなり、5月上旬の気温でした。 ミツバチは、どこからか花粉を持ってきています。きっと農家の庭先のサザンカの花粉だと思いますが、蜜も少々運んでいるのでしょうか。 月曜日からの気温上昇で、蜂の活動が活発になり、巣箱重の減少が、多くなりました。 育児も活発になり、巣内の貯蜜をどんどん消費しているようです。 近くの畑や、野原に花が咲き始める3月中旬まで、消費が続く見込みです。 昨年秋の採蜜時に、この分の貯蜜を残しておくことが重要なのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||